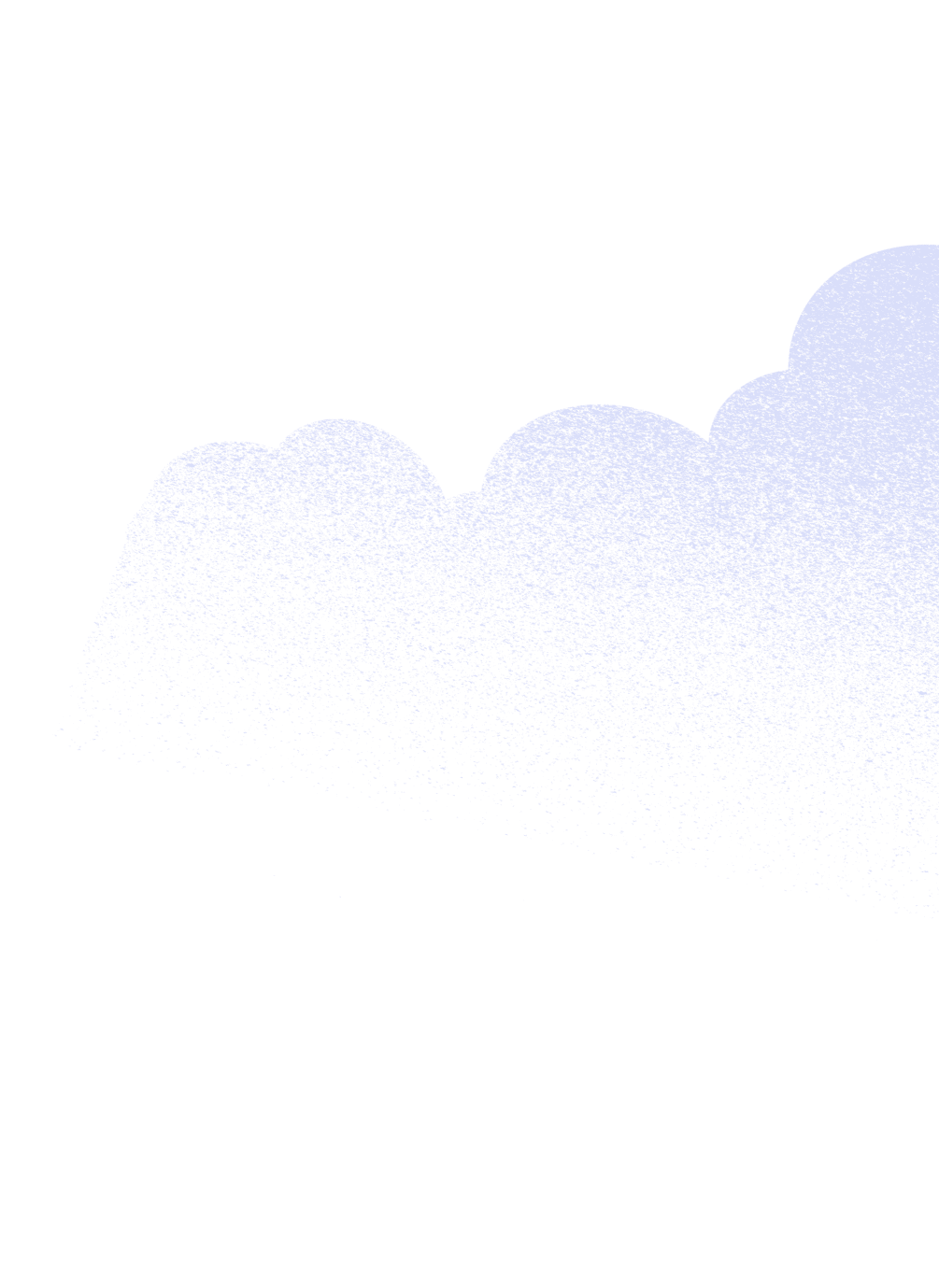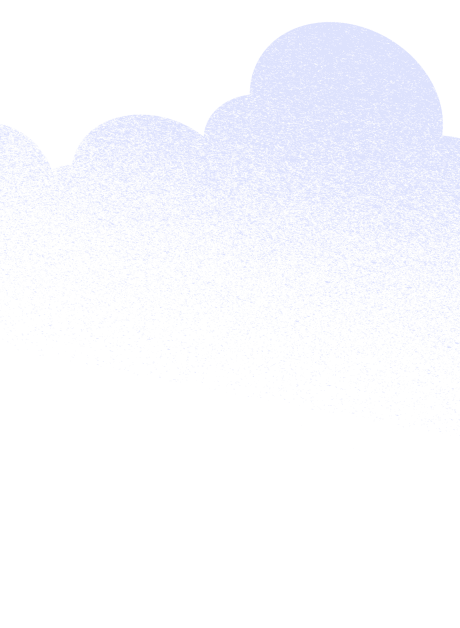日本のAI領域のトップコンサルタントとして活躍してきた森正弥さん(前職はデロイトトーマツグループ パートナー)が、博報堂DY ホールディングスが設置した新ポスト「Chief AI Officer(CAIO)」に就任しました。
20年以上にわたり、AIやデータ活用、DXの領域で第一線にいる森さんが、クリエイティブやメディアという「人間の感性」が重視される領域で、どのようなAIトラスフォーメーションをてがけていくのか。 移籍の理由やAI戦略を前編と後編にわけて掘り下げます。
信頼できる生成AIを実現するために準備すべき6つの戦略
このガイドでは以下の内容を詳しく解説しています。
・生成 AI がもたらす機会と影響
・生成 AI に関する懸念
・生成 AI に備えたデータのセキュリティ戦略




ガバナンスの次に、私がやるべきテーマはクリエイティビティ
──博報堂DYホールディングスの「Chief AI Officer」に就任された経緯をまずはお聞かせください。
森:私のキャリアは、アクセンチュア、楽天、デロイト、そして現在の博報堂DYホールディングスと続いているのですが、楽天に籍を置いていた頃から、博報堂DYホールディングスの安藤さん(安藤元博 取締役常務執行役員、CTO)と 知り合いでした。デロイト時代にも意見交換の場を度々設けていました。
約1年半前、博報堂DYグループにて新しいテクノロジーとクリエイティビティを掛け合わせていく構想を伺いました。それは博報堂DYグループの中期経営計画にも反映されていて、その中でAIは、グループを挙げた新しい取り組みを始める必要があると言及されていました。その話を聞いて、楽天やデロイトなどで培った私の経験が役に立つのではないかと、考えるようになったんです。

博報堂DYホールディングス執行役員 Chief AI Officer、Human-Centered AI Institute代表
1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、グローバルインターネット企業を経て、デロイト トーマツ グループに移籍。パートナーとしてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。東北大学 特任教授、東京大学 協創プラットフォーム開発 顧問、日本ディープラーニング協会 顧問。著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。
──過去の経歴を拝見する中で、新天地は広告業界の博報堂DYグループと聞いて驚きました。
私のキャリアを少し振り返って移籍のいきさつを話すと、最初のアクセンチュアには8年在籍していて、6年目にアクセンチュアの研究所のマネージャーに就きました。シカゴ、パロアルト、フランスのソフィア・アンティポリスに研究拠点があるなかで、パロアルトで研究者と一緒に仕事させていただく機会がありました。
それが2003-2004年頃で、ちょうどWeb2.0が出てきた時期。さまざまなビッグデータが生まれ、アクセンチュアはそのデータからAIを使った価値創出のアプローチとして、テクストマイニングやオピニオンマイニング、センティチメントアナリシスなどを当時から手がけていました。
ビッグデータの活用は、さらに広がるだろうと考えていた頃に、楽天の当時の経営陣とお会いする機会がありました。その時は、楽天が研究所の立ち上げを行うタイミングで、私がアクセンチュアの研究所でマネージャーもやっていたことが目に止まり、研究開発をリードするべく楽天に入りました。
そこから楽天の事業や知的生産活動をAIで変革する取り組みに14年間従事し、世界5か国7拠点に研究所を設けて、世界中から150名以上のPhDを集めて、楽天のさまざまなサービスやバックボーンの基盤や新規事業を生み出しました。

いろんな経験を積んでいる中で、2015年以降になり、時代の変化の兆しを感じ始めたんです。それまでのテクノロジーでディスラプション(創造的破壊)を起こし新しいサービスを作っていく流れに陰りが見え始めてきたのです。
プライバシーの問題は以前から議論されていましたし、フェイクニュースやソーシャルメディアを通した世論操作などが注目されるなかで、テクノロジーの功罪が議論されるようになった。同時に、AIの倫理問題も見えてくるようになりました。
私自身も、単なるテクノロジーの活用でイノベーションを起こすことだけではなく、より人間的な側面に依ったガバナンスが必要になると考えるようになりました。
「テクノロジーの活用」と「ガバナンス」を組み合わせた、企業における新しい技術のあり方を追求することで、今後の生活者や社会に受け入れられるビジネスを生み出していこう、と。
そこで、楽天を辞め、さまざまな企業とお話をする中で、テクノロジーの活用とガバナンスを組み合わせることは、デロイトトーマツグループのノウハウを生かせばできるというところで、デロイトに参画しました。
グループ横断でのそうした組織も作り、色々な企業や産業の支援をしました。また、公的な規制に関わる弁護士や大学の先生との研究会の座長をデロイトグループが務めるなど、一定の成果が出せたと思っています。
そうした流れの中で、先ほどの安藤さんとの意見交換があり、「ガバナンスの次に私がやるべきテーマはクリエイティビティだ」と。
私自身、2018年頃に、将来は「Creative AI」というジャンルが出てくるという発信を講演やメディアを通じてしていて、クリエイティビティを持ったAIが登場し、AIがさまざまな創作活動の領域にも使われるようになる、と予見していました。
──今で言うGenerative AI(生成AI)ですね。
Generativeという言葉自体は当時からあったのですが、学術用語だったので流行らないだろうと思ってCreative AIという言葉を使っていました。
デロイトでテクノロジーとガバナンスに取り組んでいる間は、そのテーマは寝かせていました。ですが、生成AI、特に「Midjourney」や「Stable Diffusion」、そして「ChatGPT」が登場し、テキストだけでなくブレーンストーミングやアイデア創出にも影響を与えるようになった時に、予想以上に生成AIのインパクトの大きさを感じました。人の知的活動を超えて、創造活動にまでAIが入り込むことへの脅威論も出始めました。
博報堂DY グループがクリエイティビティとテクノロジーの掛け算を戦略に入れ、今期から「クリエイティビティ・プラットフォーム」を目指す姿に掲げている中で、博報堂DYグループもクリエイティビティとAIの関係性をきちんと把握し、業界の代表としてメッセージを発信する必要があると強く感じました。
そこに私なりに貢献できればと思い、博報堂DY ホールディングスへの参画を決断した次第です。

新ポスト「CAIO」は何に取り組むのか
──CAIOに就任して1か月半ほど経ちましたが、ご自身の発見や得られた感触を教えてください。
グループ各社を見てみると、各社にAIのチームやリーダーがいてたくさんの取り組みを活発に行っていました。
それぞれがAIの技術を活かしていて、内部でのAIやRAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)の活用なども行われています。そういった個々の潜在能力やアセット、技術力は確かにあると強く感じました。
例として、博報堂DYグループは「生活者発想」というフィロソフィーのもと、生活者起点のビジネスを大切にしていますが、その中で生活者の意識調査やデータ分析を使って生活者の理解を深めており、その延長として7000人の生活者ペルソナと会話ができる生成AIのサービスがあったりもします。
また、ちょっとエンタメ的な面白いユースケースに「AIラップ名刺」というものもあります。自分のプロフィールを、生成AIで作成し顔写真をアップロードすると、自分を表現するパンチラインが効いたラップを生成してくれて、自分の顔写真とリップシンクしているように歌ってくれる。それを名刺として交換できるものなのですが、クリエイティビティとAIを組み合わせたアプリケーションの一例でしょう。
重要なのは、いかに博報堂DYグループ全体の力としてAIを今後の成長のエンジンにしていくかだと思っております。
──CAIOというポジションは、海外では徐々に浸透していますが、日本では馴染みがないポジションです。CDOでもCIOやCTOでもない、CAIOという役職を森さんご自身はどのように捉えていらっしゃいますか。
CAIOの役割は、主に2つあると感じています。
1点目は、短中期的に「AIを使って自分たちがどのような方向に向かうのか」「AI を用いてどう変わっていくのか」を指し示すこと。
企業と顧客との間の様々な接点でビジネスが行われる中で、過去おおよそ20年間にわたり、データが蓄積されてきています。
そうしたデータをベースにして、新しいことをどのように作っていくかを進める「エンジン」として、AIが使われるようになり、さまざまなユースケースの開発が可能になってきた。AIの特徴を理解した上で、事業や企業の成長をどう進めていくかを考えていくのが、CAIOとしての重要な側面の1つです。
2つ目は、長期的にAIの未来を的確に見据えることです。AIは今後も急速に変化していくでしょう。その動きを追い、未来を想像したうえで、自社にとって有効なAI戦略は何かを定める。それがCAIOにはもとめられるでしょう。

──その2つに集中するという意味でCDOやCTOと異なるのですね。企業によってはCDOの傘下にAIの専門チームを置くパターンがあると思いますが、AIというテクノロジーのインパクトの大きさを考えると、それをリードする人や組織は独立させるべきなのでしょうか。
企業の課題がどこにあるかによって、組織のカタチは変わってくると思います。例えば、顧客視点で新しいマーケットをデジタルでどう作るかという点に重きを置いている場合は、CDOのほうが重要性が高く、その中にCAIOがいるほうが自然です。
あるいは、そもそも全社的に変革しなければいけない領域が明らかに見えている状況であれば、Chief Transformation Officerが必要で、その下にCAIOがいるということもあるでしょう。
また、CTOの下にCAIOがいるというパターンも会社の状況によってはあるかもしれません。
──博報堂DY ホールディングスにとってCAIOは新ポスト。森さんからCAIOのポジション設置を要求されたのでしょうか。
いえ、博報堂DYグループとのディスカッションの中で出てきたアイデアです。私自身は当初、トランスフォーメーションの役割を担うでもいいかなと思っていました。
これまでのキャリアの中で、実は研究開発のほかに、DXの全社プロジェクトも楽天時代にリードすることもありましたし、デロイトでも顧客企業のDX推進担当を務めていましたので。
クリエイティビティとテクノロジー、クリエイティビティとAIについてディスカッションを進める中で、これからは特に生成AIによってクリエイティビティのあり方が変わっていくはずだという話になりました。
そうした時に、AIを単なる道具として考えるのではなく、「AIは人のクリエイティビティを引き出すもの」として考えるべきという発想が、もともと博報堂DYグループの中にあって、それは私も非常に重要だと思ったのです。
ですから、私からリクエストしたのではなく、話し合いの中でCAIOのようなポジションが必要だよね、という話に落ち着いた感じですね。そこに私が収まるのが一番物事を進めやすいだろうと。
──なるほど。それでは、これからは森さんの頭の中、AI戦略についてお伺いしたいと思います。
*後編に続きます。後編では、森さんが描くAI戦略についてご紹介しています。
取材・執筆:池上雄太 小澤健祐、撮影:小澤健祐、編集:木村剛士
AI戦略ガイド
CRM + AI + データを信頼の方程式に