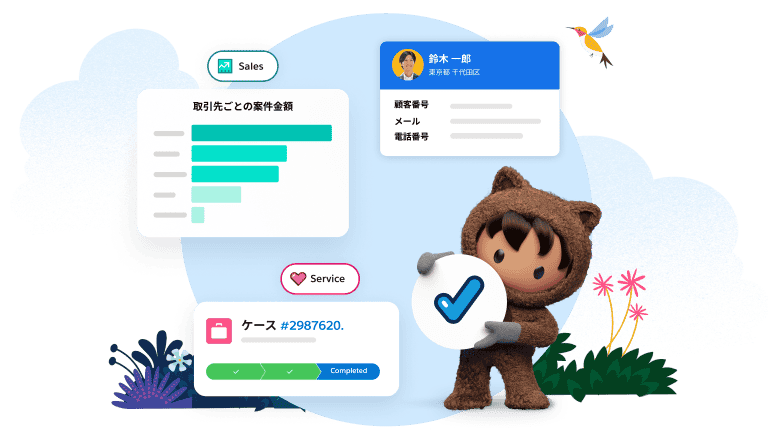案件管理とは?メリットや管理ツールの種類、選び方も詳しく解説
「あの案件、どうなった?」「最新の顧客情報がどこにあるかわからない…」 日々の案件管理で、このようなお悩みを抱えていませんか?
Excelやスプレッドシートでの管理に限界を感じ、チーム内での情報共有や進捗把握の難しさにお困りの営業マネージャーやチームリーダーの方は少なくないはずです。
営業活動では案件を適切に管理し、進捗状況や顧客情報などを把握する「案件管理」が重要です。正しく管理することで、適切なタイミングで効果的なアプローチができるようになります。
本記事では、そんな皆様のために、案件情報の属人化を防ぎ、チーム全体の営業効率と成果を飛躍的に向上させるための具体的なステップを徹底解説します。案件管理の基本から、自社にぴったりのツールを選び、効果的に活用するためのポイントまで、明日から実践できるノウハウをお届けします。
この記事を読めば、煩雑な案件管理から解放され、より戦略的な営業活動に集中するための道筋が見えるはずです。
案件管理とは案件の進捗状況や顧客情報を管理すること

案件管理とは、営業活動で獲得した案件の進捗や顧客情報を管理する取り組みです。案件に関する情報は多岐に渡り、自社製品の情報や企画書、顧客とのコミュニケーションなどアプローチに活用できる材料を正しく管理する必要があります。
案件管理を実施するうえでは、目的・必要性や管理に必要な情報を理解することが大切です。
以下で案件管理の目的や必要な管理項目について紹介します。
案件管理の目的・必要性
案件管理は、営業活動の進捗や顧客情報など案件に関わる情報を可視化するために必要な業務です。
案件に関する情報がどこにあるかわからない状態では、案件の進捗やアプローチに必要な情報を把握できません。
進捗に応じて適切なタイミングでアプローチしたり、顧客情報からアプローチ方法を検討したりするために案件の情報を整理するのが、案件管理の目的です。
より効果的なアプローチを実施するためには、案件一つひとつを正しく管理し、営業活動に必要な情報をすべて把握できている状態にしましょう。
案件管理に必要な項目
案件管理に必要な項目の例は、以下のとおりです。
- 取引先名
- 商談日
- 担当営業
- 対象商材
- 商談の経緯
- 商談の内容
- 受注予定日
- 見込額
- 受注角度
- 商談の進捗
- 担当営業の行動履歴
顧客情報や提案する商材、担当営業の行動履歴などを管理し、案件の現状が一目でわかるように整理します。
案件別に管理できていると管理者が各案件の進捗をチェックでき、担当営業が不在の場合も別のスタッフが対応できるようになります。
上記の項目はあくまで例であり、案件によって管理すべき情報が変わる点に注意が必要です。各企業で取り扱う情報が異なるため、自社が必要とする情報に絞り込んで案件を管理しましょう。
案件管理と商談管理の違い

案件管理と商談管理は同じ意味で使われる場合もありますが、異なる業務として捉える場合もある点に注意しましょう。
案件管理は各案件に関わるすべての情報を管理するため、案件名や顧客の基本情報など幅広い項目を取り扱います。各案件の記録を残し、アプローチの質向上や失注の防止などを図るのが主な目的です。
一方、商談管理は商談に関する情報を中心に取り扱います。商談の進捗状況や受注確率などが主な項目で、商談化から成立までのプロセスを管理し、成約率を高めるのが目的です。
「案件管理は案件全体の情報」「商談管理は商談のみの情報」と管理する範囲が異なる点を理解し、正しく使い分けましょう。
案件管理の怠りが招く5つの問題
「うちのチームは、なんとなく案件管理できているから大丈夫」…本当にそうでしょうか?
日々の忙しさの中で見過ごされがちな案件管理の不備は、気づかぬうちに深刻な問題を引き起こし、チームの成果やモチベーションにネガティブな影響を与えているかもしれません。
案件情報がブラックボックス化している
- 担当者しか案件の進捗や顧客との詳細なやり取りを把握しておらず、上司や同僚は状況が全く見えない。
- 病欠や会議など、急な担当者不在時に他の誰も対応できず、顧客対応が遅れてしまう。
- 担当者が退職する際に、案件情報が適切に引き継がれず、最悪の場合、失注や顧客離れにつながる。
- 最新情報が反映されていない古い資料や報告書をもとに、誤った経営判断を下してしまうリスクがある。
本来の業務を圧迫する報告業務の負担が大きい
- 各担当者が個別のフォーマットで報告するため、マネージャーが集計・取りまとめに何時間も追われている。
- 報告書作成が目的化し、数字の見た目を整える作業に終始。分析や次のアクションに繋がらない。
- リアルタイムな状況が把握できないため、問題発生から報告までにタイムラグが生じ、対応が後手に回る。
- 営業担当者が報告書作成に時間を取られ、本来注力すべき顧客対応や新規開拓の時間が削られている。
案件の抜け漏れ・対応遅延が頻発している
- 対応すべきタスクやアポイントメントが誰にも共有されず、気づいたときには手遅れになっている。
- 複数の案件を抱える中で、優先順位付けが曖昧になり、重要な案件への対応が遅れてしまう。
- 顧客からの問い合わせや要望が担当者止まりで、チームとして迅速かつ的確な対応ができない。
- 結果として、顧客満足度が低下し、競合他社に案件を奪われる原因となる。
ノウハウが属人化している
- 個々の営業担当者の成功事例や失敗事例が共有されず、同じようなミスが繰り返される。
- 新人や若手メンバーが、先輩のノウハウを学ぶ機会が少なく、育成に時間がかかる。
- 営業スタイルが担当者ごとにバラバラで、組織としての営業力・提案力が底上げされない。
- 異動や退職によって、貴重な営業ノウハウや顧客との関係性が失われてしまう。
勘と経験頼みの行き当たりばったりで経営している
- 確度、金額、進捗フェーズなどの正確な案件データが蓄積・分析されていないため、客観的な売上予測が立てられない。
- どの市場・顧客層に注力すべきか、どのような提案が効果的かといった戦略が、データにもとづかず曖昧になる。
- 営業活動のボトルネックがどこにあるのかを特定できず、具体的な改善策を打てない。
- 結果として、場当たり的な営業活動に終始し、安定的な事業成長が見込めない。
これらの問題点に一つでも心当たりがあるなら、それは案件管理の仕組みを見直すサインかもしれません。次の章では、これらの課題を解決し、案件管理を成功させるための具体的なメリットについて解説します。
案件管理の実施による5つのメリット

案件管理の実施で、以下のメリットが期待されます。
- 案件の性質を見極め、受注確度を高める
- 属人性を排除し、営業を組織化できる
- 高精度の確度と見込契約額で、経営上の意思決定がしやすくなる
- 他部署・部門と円滑に連携できる
- 案件の分析結果を業務・体制の改善に役立てられる
受注確度の向上や属人化の防止以外にも、情報共有や体制の改善などにも役立つため、メリットを理解したうえで案件管理を営業組織に取り入れましょう。
案件の性質を見極め、受注確度を高める
案件管理で顧客から得た情報を整理することで、案件の性質を見極められます。先方のニーズや興味・関心などに合わせて、適切なタイミングで最適なアクションを取れるようになるのがメリットです。
マネージャーも、営業担当者へ状況に合った的確な指示やアドバイスができるため、受注確度の向上が見込めます。
属人性を排除し、営業を組織化できる
案件情報の可視化・共有で、営業組織の属人性を排除できます。担当者しか案件情報を知らない状態を避けられ、営業活動の質を均一化できるのがメリットです。
どの担当者も案件情報を駆使した営業ができるだけでなく、担当者不在時に別のスタッフが柔軟に対応できるようになります。案件管理によって組織的な営業活動を可能にし、チームで成果を高められる営業組織を実現できるでしょう。
高精度の確度と見込契約額で、経営上の意思決定がしやすくなる
各案件の見込額と精度の高い受注確度があれば、高精度の売上予測が立てられます。
営業担当者、営業部門全体での目標設定が適切にできるようになり、組織の意思決定の円滑化が可能です。
また、結果として残る数字だけでなく、プロセスも記録することで、一人ひとりの行動や実績を正しく評価できます。
他部署・部門と円滑に連携できる
複数の部署・部門にまたがる案件を抱えている場合は、案件管理で円滑な連携を図れるのがメリットです。
案件に関連する情報をすべてまとめ、全体で連携できる体制を整えると、どの部署・部門からも必要な情報を確認できます。
進捗も全体で共有できるため案件を円滑に進められ、行き当たりばったりの判断でトラブルが起きるリスクを抑えられます。
案件の分析結果を業務・体制の改善に役立てられる
案件管理を実施すると、営業活動に役立つデータが蓄積され、業務や体制の改善を進められます。
たとえば、案件の失注が増えている場合にアプローチまでの期間にバラつきがあったとすると「〇日以内に初回アプローチ」といった対策を講じられます。
また、顧客情報も業務改善に効果的なデータであり、案件の傾向を見極める際に便利です。顧客の業種や課題などの共通点が明らかになれば、より効果的な戦略を検討できます。
案件管理で気をつけたい3つのデメリット

案件管理には多くのメリットがありますが、運用次第では以下のデメリットが生じるため気をつけなければいけません。
- 運用体制が整っていないと機能しない
- 要件定義が甘いと状況を正しく把握できない
- セキュリティ意識が低いとトラブルのリスクが高まる
メリットを得られないだけではなく、トラブルにつながるおそれもあるため、あらかじめデメリットへの対策を講じましょう。
運用体制が整っていないと機能しない
案件管理は案件に関わる情報を入力・更新しなければ機能しません。導入当初はこまめに入力していても、徐々に頻度が減り、活用されなくなる場合もあります。
案件管理を機能させるためには、運用体制の構築が欠かせません。営業担当者の負担が大きくならないよう簡単に入力できるよう、入力項目や入力内容を工夫したり、入力の時間を確保したりするなど、組織全体で取り組みましょう。
また、案件管理を開始する際に目的を共有することも大切です。運用目的が明らかになれば、案件管理に必要性が生まれ、こまめに入力する習慣をつくりやすくなります。
要件定義が甘いと状況を正しく把握できない
要件定義とは、言葉の意味や条件などを明確に定義することで、不十分なまま案件管理を実施すると運用が難しくなります。
たとえば、案件の進捗を「商談中」と入力する際に、何を商談とするかを明確に決めなくてはなりません。Aさんは資料の受け渡し、Bさんは電話での説明のように個人の認識が異なると、進捗管理の精度が低くなります。
営業組織全体で案件の認識を統一するためには「商談中」「成約」といった言葉の定義を明確にすることが重要です。
セキュリティ意識が低いとトラブルのリスクが高まる
案件管理で取り扱う情報は、外部に漏洩してはいけない機密情報を多く含んでいます。担当者のセキュリティ意識が低いと、重要な情報が漏えいするリスクがある点に注意が必要です。
営業担当者個人のパソコンで管理したり、不特定多数が集まる場所で管理画面を見たりした場合、案件情報の紛失や流出を起こすおそれがあります。
とくにパソコンのローカルディスクやUSBメモリのようなポータブルメディアは危険です。盗難や紛失、ウイルス感染などによって情報漏えいするリスクも少なくありません。
機密情報を守りながら案件管理するには、セキュリティ性に優れたSaaaSを導入することも検討しましょう。
案件管理ツールの種類

案件管理を実施する際は、ツールを活用するのが一般的です。ツール上に顧客情報や進捗などを記録し、必要に応じて情報の確認や更新を行います。
ツールには種類があり、特徴や使い方が異なるため、効率的な案件管理を実施するためにはツール選びが重要です。
主な案件管理ツールには、以下の6つが挙げられます。
- Excel
- タスク管理ツール
- 業務改善プラットフォーム(ノーコード・ローコードツール)
- CRM
- SFA
- MA+SFA
各ツールのメリット・デメリットを理解し、課題や目的にあったツールを検討しましょう。
営業管理ツールを使用する目的や選び方は以下の記事で解説しているため、あわせて参考にしてください。
Excel
Excelは、大半のPCにインストール済みで誰でも扱えるため、比較的簡単に案件管理を行えます。
しかし、Excelはあくまでも表計算ソフトです。案件管理で必要な「時系列での管理」ができず、入力したデータの紐づけや分析には対応できません。複数のファイルに分割されていると、データの検索も不自由です。
また「客観的評価がしにくい」のもデメリットです。各案件の受注確度や営業活動による案件フェーズは、おもにマネージャーによる客観的評価によって、その精度を高めていきます。
しかし、Excelによる管理では、これらの項目評価は担当者の主観的な感覚と判断に頼るほかなく、「管理上のフェーズは進んでいるが、内実が伴っていない」という乖離が起こる危険性があります。
Excelによる案件管理の利点は、「導入の手軽さ」を除いてほとんどなく、むしろデメリットばかりが目についてしまうのです。
デメリットが目立つものの、活用方法によっては顧客管理に役立てられます。エクセルを用いた顧客管理は以下の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてください。
▶ エクセル(Excel)を活用した顧客管理方法|データベースの作り方も解説
また、Excelは営業管理にも使用できるため、営業支援ツールであるSFAとどちらがよいか迷っている方も多いのではないでしょうか。SFAとExcelの違いは、以下の記事をチェックしましょう。
タスク管理ツール
タスク管理ツールには、さまざまな種類があります。いずれも複数メンバーが協働するプロジェクト全体の進行を管理し、さらに個々のメンバーの行動を管理するための実用的な機能が備わっています。
ガントチャートやバーンダウンチャートなど、時系列に沿って行動を記録する機能は、チームワークの管理ツールとして有用です。チームと個人それぞれのタスクを明確にでき、入力した情報は即時に共有できるため、プロジェクトの進行管理に十分なパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。
しかし、あくまでもタスク管理、個人と組織の行動を管理するものであって、案件の管理の機能は不十分です。
新規導入の候補に入っているなら「そのツールを何のために導入するのか」という原点に立ち返り、改めて検討し直す必要があるでしょう。
タスク管理の方法は以下の記事で解説しているため、あわせて確認しましょう。
業務改善プラットフォーム(ノーコード・ローコードツール)
プログラミングの専門知識がなくても、自社の業務に合わせて必要な業務アプリケーション(案件管理アプリも含む)を比較的自由に構築・カスタマイズできるツールです。
独自の管理項目や業務フローに柔軟に対応したシステムを内製できること、さらにスモールスタートしやすく、状況に合わせて段階的に機能を拡張できることが特徴です。
業務改善プラットフォームは、既存のパッケージソフトでは自社の特殊な業務にフィットしないと感じている企業や、Excelやスプレッドシートでの管理から脱却し、より効率的かつ柔軟なシステムを低コストで実現したい企業におすすめです。
ただし、高度な機能や複雑なロジックを実現するには、ある程度の設計スキルや知識が必要になる場合がある点には注意しましょう。
CRM
CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)は、顧客情報の管理に優れたツールです。顧客の基本情報をはじめとして、購買履歴や購入額などの詳細なデータも管理できます。
顧客に関わる情報を一元管理できるため、営業活動に必要な情報を全体に共有しながら、他部署・部門との連携も図れるのがメリットです。蓄積した顧客情報は新規顧客へのアプローチに活用できるだけではなく、既存顧客へのフォローにも効果を発揮します。顧客の行動に応じて適切なフォローを行えば、優良な既存顧客へと育成できるでしょう。
案件管理との相性がよいものの、導入しただけでは効果を発揮できません。案件情報をこまめに入力・更新する体制を整え、データの活用・分析を積極的に行うことが重要です。
CRMのメリットと効果を発揮する方法は以下の記事で解説しているため、あわせて参考にしてください。
さまざまなCRMがある中で、案件管理に活用しやすいのが「Starter Suite」です。月額3,000円のリーズナブルな料金で導入でき、案件の進捗状況や顧客情報を管理できます。
顧客のメールを自動で同期したり、顧客の問い合わせを管理したりできるのも特徴です。無料トライアルを実施しているため、案件や顧客の管理を効率化したい方はお気軽にお試しください。
SFA
SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)は、営業活動全般に関わる情報を一元管理し、チームメンバー間で共有できるツールです。案件管理の機能はもちろん、入力された情報はお互いに関連づけられ、リアルタイムで更新・共有されます。
SFAは、単に案件の進捗を管理するだけでなく、受注確度や見込額などの管理も可能です。そのため、受注確度に合わせた対応策を打ったり、特定期間での売上予測を立てて経営に活かしたりと、データを行動に結びつけやすくなります。
ただ、ほかの多くのツールと同様、導入してもきちんと運用できないとメリットを発揮してくれません。導入にあたっては無理のない規模を設定し、サポートが充実した製品を選ぶなどの工夫も必要です。
SFAのメリット・デメリットは以下の記事で解説しているため、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
MA+SFA
SFAは案件を管理するには最適なツールですが、マーケティングの段階から管理できれば、マーケティングとセールスを横断した案件の一元管理が可能になります。
案件の一元管理を実現するには、SFAに加えてMA(マーケティングオートメーション)を導入するのが効果的です。
MAは、見込み顧客を獲得・育成し、受注確度の高いホットリードとしてセールスに引き渡すまでのプロセスを管理します。
SFAとMAを導入することで、クライアントと接触してから商談を経て成約に至るまでのプロセスを記録・管理できます。アフターセールスの領域でも存分に活用でき、LTV(顧客生涯価値)の増大にも貢献してくれるでしょう。
MAのメリット・デメリットや運用方法は以下の記事で解説しているため、SFAとの併用を検討する際にぜひチェックしてください。
案件管理ツールの選び方

自社に導入する案件管理ツールを検討する際は、以下のポイントに注目しましょう。
- 導入目的と解決したい課題は明確か
- 必要な機能に過不足はないか
- 初期費用とランニングコストの費用対効果は見合うか
- スムーズに導入できるか
- スマホやタブレットでも使用できるか
- 誰でも使いやすく見やすいか
- 既存システム・ツールと連携できるか
- サポート体制は十分か
- 将来的な拡張性やカスタマイズ性はどうか
導入のしやすさや使いやすさなどを確認し、自社と相性のよいツールを選びましょう。
導入目的と解決したい課題は明確か
「なぜ案件管理ツールを導入するのか」「案件管理ツールで何を解決したいのか」という目的を具体的にしましょう。
「営業報告の手間を半減させたい」「失注原因を分析して成約率を10%上げたい」など、具体的な目標を設定することで、必要な機能や案件管理ツールのタイプが見えてきます。
必要な機能に過不足はないか
目的達成のために「絶対に譲れない機能(Must-have)」と「あったら嬉しい機能(Nice-to-have)」を整理しましょう。
多機能すぎても使いこなせずコストが無駄になることもあるため、現場の担当者の意見も聞き、本当に必要な機能を見極めます。
初期費用とランニングコストの費用対効果は見合うか
初期費用だけでなく、月額・年額の利用料、ユーザー数に応じた料金体系、オプション機能の費用など、総コストを把握しましょう。
そして、業務効率化、売上向上など、案件管理ツールのコストに見合うだけの効果が期待できるかを慎重に検討します。
スムーズに導入できるか
案件管理は、顧客情報管理や営業活動の効率化などに欠かせないため、できるだけスムーズに導入できるツールを選びましょう。
ツールには自社サーバーに設置するオンプレミス型、インターネット上で利用できるクラウド型に分けられます。
オンプレミス型は自社サーバーの設置に費用や時間がかかるため、導入コストを抑えたい方はクラウド型がおすすめです。設定の手間や時間が少なく、初期費用も抑えやすいため、スムーズな導入が可能です。
スマホやタブレットでも使用できるか
案件に関する情報を必要なタイミングで確認したり、すき間時間に入力したりするためには、モバイル対応したツールが便利です。
スマホやタブレットからツールにアクセスできると、訪問前に顧客情報を確認でき、営業活動後すぐに情報を入力できます。
モバイルデバイスから迅速に案件情報を記録できると、各部門・スタッフとのリアルタイムな情報共有が可能です。
注意点として、多機能なツールはモバイルデバイスでは視認性が低下するおそれがあります。スマホやタブレットに対応しているだけではなく、見やすさや使いやすさも確認しましょう。
誰でも使いやすく見やすいか
案件管理の効果を発揮するためには、誰でも使いやすく見やすいツールを選びましょう。データが入力しやすいか、画面が見やすいかなどを確認し、スキルに関わらず使いこなせるツールを選ぶのが重要です。
使いやすさや見やすさをチェックするためには、体験デモや無料トライアルなどで使用してみるとよいでしょう。いくつかツールを試し、もっとも使いやすいツールを選ぶのがポイントです。
既存システム・ツールと連携できるか
すでにシステム・ツールを活用している場合は、それらと連携できる案件管理ツールを選びましょう。
連携できるツールを選べば、導入時に必要なデータを一括で移行できます。導入後もひとつのツールに案件の情報を統合できるため、情報共有に効果的です。
既存のシステム・ツールを確認したうえで、連携に対応している案件管理ツールを選びましょう。
サポート体制は十分か
案件管理ツール導入時の設定サポートや操作方法に関する問い合わせ窓口、トラブル発生時の対応など、ベンダーのサポート体制を確認しましょう。
日本語でのサポートが受けられるか、FAQやマニュアルが充実しているかもポイントです。同業種・同規模の企業での導入実績も参考になります。
将来的な拡張性やカスタマイズ性はどうか
現在の課題解決だけでなく、たとえばユーザー数や機能の追加、管理項目の変更など、将来的な事業拡大や業務変化にも対応できるかも考慮しておくと安心です。
自社の業務に合わせて、どこまで柔軟にカスタマイズできる案件管理ツールかも確認しましょう。
これらのポイントを踏まえ、複数の案件管理ツールを比較検討し、資料請求や無料トライアルを積極的に活用して、自社にとって最適なパートナーとなる案件管理ツールを見つけ出してください。
本格的な案件管理ツールの導入が早いと感じた方へ
「チームも小さいし、まだ本格的な案件管理ツールを導入するほどでは…」「まずは、今使っているExcelでの管理方法をもう少し改善できないだろうか?」 このように感じている営業マネージャーやチームリーダーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たしかに、Excelやスプレッドシートは、特別なコストをかけずに手軽に始められる案件管理の手段です。しかし、その手軽さゆえの限界も存在します。
この章では、まずExcelでの案件管理を少しでも効率化するための具体的な工夫と、それでもなお直面するであろう壁、そしてその壁を乗り越え、無理なく次のステップである案件管理ツール導入へと進むための考え方について解説します。
Excel・スプレッドシートでの案件管理を効率化する3つのコツ
本格的な案件管理ツール導入を検討する前に、まずは現在のExcelやスプレッドシートでの管理方法に、以下のような改善を加えるだけでも、現状よりは格段に使いやすくなるはずです。
コツ1:管理項目を標準化し、入力ルールを明確に定める
以下に代表されるような、基本的な管理項目をチーム内で統一しましょう。
- 案件名
- 顧客名
- 担当者
- 進捗フェーズ(例:アポ取得、提案中、クロージングなど)
- 確度(A,B,Cなど)
- 受注予定日
- 受注予定金額
- 次回アクション
- 備考
たとえば日付の書式や金額の単位、進捗フェーズの定義など、各項目の入力ルールを明確にし、誰が入力しても同じ基準で情報が蓄積されるようにします。Excelの入力規則やプルダウンリスト機能を活用すると、入力ミスや表記の揺れを防ぎやすくなります。
コツ2:最新版は常にオンラインで共有し、共同編集できる環境を作る
作成した案件管理表のExcelファイルを個人のPCやファイルサーバーの奥深くに保存していては、情報共有は進みません。
GoogleスプレッドシートやMicrosoft 365のExcel Onlineなどを活用し、クラウド上で常に最新版を共有し、複数メンバーが同時に閲覧・編集できる環境を整えましょう。
また、ファイル名に「案件管理表_202X年X月_vX.X_最新版」といった命名規則を設けたり、更新履歴を備考欄に記載したりする運用ルールも有効です。
コツ3:定期的な更新と「案件の棚卸し」をチームの習慣にする
どんなに素晴らしい案件管理のフォーマットを作成しても、情報が古ければ意味がありません。週に一度の営業会議前や、毎日の朝礼後など、チームで案件情報を更新するタイミングを決め、それを習慣化することが重要です。
また、長期間進捗のない案件や、正式に失注となった案件は、いつまでもアクティブな案件リストに残さず、「クローズ案件」シートに移動するなどして定期的に「棚卸し」を行ないましょう。これにより、本当に注力すべき案件が見やすくなります。
Excel・スプレッドシートでの案件管理で直面する5つの限界
| リアルタイムな情報共有と複数人でのスムーズな同時作業の難しさ | クラウドサービスを利用しても、大人数が同時に頻繁に更新作業を行なうと、処理が重くなったり、入力内容が競合したりする場合があります。また、誰がいつどこを更新したのか、変更履歴を詳細に追跡することも専用ツールほど容易ではありません。 |
| 手入力による手間、入力ミスや漏れの発生リスク | すべての情報を手作業で入力するため、どうしても入力ミスや記載漏れが発生しやすくなります。また、関数や数式が複雑に絡み合ったシートは、一部を誤って編集してしまうと全体が壊れるリスクも抱えています。 |
| 高度なデータ分析やレポート作成の制約 | ピボットテーブルなどを使えばある程度の集計やグラフ化は可能ですが、営業活動全体の傾向分析や多角的な売上予測、担当者別や製品別のパフォーマンス分析などを、柔軟かつスピーディーに行なうには限界があります。 |
| 他の業務システムとのデータ連携の難しさ 例:カレンダー、メール、会計ソフト |
案件情報と関連するスケジュール(アポイントメント)、顧客とのメールのやり取り、作成した見積書や請求書のデータなどを、案件管理表と一元的に紐づけて管理することが難しく、情報があちこちに散在しがちです。 |
| 属人化の完全な排除は困難、セキュリティ面での不安 | 高度な関数やマクロを組んで効率化を図ったとしても、その知識やメンテナンスが特定の人に依存してしまいがちです。また、ファイルベースでの管理は、誤削除や不正な持ち出しといったセキュリティリスクも伴います。 |
案件管理ツール導入を検討する適切なタイミングとスムーズな移行の考え方
| 「Excelではもう業務が回らない」という状況になる前に検討を始める | 問題が深刻化し、現場が疲弊しきってから慌てて案件管理ツールを探し始めるのではなく、少し余裕のある段階で情報収集や比較検討をスタートするのが理想的です。 |
| 最初からすべての機能を完璧に使いこなそうとしない | たとえば、案件情報の共有漏れを防ぎたい、報告業務を効率化したいなど、まずはチームが抱える最も大きな課題を解決できるシンプルな機能からスモールスタートできる案件管理ツールを選ぶのも一つの有効な手段です。 |
| 現場の心理的なハードルを下げる工夫を凝らす | 新しいツールの導入には、多かれ少なかれ現場からの戸惑いや使い方を覚えることへの抵抗感が伴います。導入の目的やメリットを丁寧に説明し、操作が直感的で分かりやすく、現在の業務フローを大幅に変えなくても導入できるような案件管理ツールを選ぶことが、スムーズな移行の鍵となります。 |
| 無料トライアルやデモンストレーションを積極的に活用する | 多くのツールベンダーが、無料の試用期間や製品デモンストレーションを提供しています。実際に自分たちの手で操作感を試し、自社の業務に本当にフィットするのか、疑問点を直接ベンダーに確認する良い機会となります。 |
Excelやスプレッドシートでの案件管理を通じて得た「自社にとってどのような情報が必要か」「どのような管理が理想か」といった経験は、より高度な案件管理ツールを選ぶうえで必ず役立ちます。
現状の課題と理想の姿を明確にし、無理のないステップで案件管理ツールの活用へと進んでいきましょう。
案件管理ツールを成果に繋げるための実践ロードマップ
「高機能な案件管理ツールを導入したのに、現場でなかなか活用されない…」「期待したほどの導入効果が出ていない…」 このようなお悩みは、実は多くの企業で聞かれる声です。
優れた案件管理ツールを選ぶことはもちろん重要ですが、それ以上にツールを組織にしっかりと定着させ、継続的に活用していくための計画的な取り組みが成功の鍵を握ります。
ここでは、案件管理ツールの導入プロジェクトを成功させ、その効果を最大限に引き出すための実践ロードマップを、3つの主要なフェーズに分けて具体的に解説します。
フェーズ1:徹底した導入準備フェーズ
案件管理ツール選定が完了し、導入へと気持ちが高まる時期ですが、この導入準備フェーズこそ、プロジェクトの成否を左右する最も重要な期間です。
焦らず、以下のポイントを確実に押さえましょう。
| 1. プロジェクトチームの発足と推進体制の確立 | 案件管理ツールの導入は、単なるシステム導入ではなく「業務改革プロジェクト」と捉えましょう。営業部門の現場担当者やマネージャー、情報システム部門、場合によっては経営層も巻き込んだプロジェクトチームを発足させます。 プロジェクト全体の推進責任者を明確にし、各部門との調整や意思決定をスムーズに行なえる体制を構築します。 |
| 2. 明確な導入目的とKPI(重要業績評価指標)の再確認と共有 | 「なぜこのツールを導入するのか?」「導入によって、具体的に何を、いつまでに、どの程度改善したいのか?」という目的とゴールを、プロジェクトチーム内はもちろん、全社的に改めて共有し、共通認識を醸成します。 例:「案件情報の入力・共有漏れを現状の50%削減」「営業報告資料の作成時間を月平均10時間削減」「新規顧客の成約率を3ヶ月後までに5%向上」など、測定可能で具体的なKPIを設定することが、後の効果検証と改善活動に不可欠です。 |
| 3. 現状の業務フローの徹底的な洗い出しと理想の業務フロー設計 | 現在の案件発生から受注、アフターフォローに至るまでの業務フローを詳細に書き出し、どこにボトルネックや非効率が存在するのか、誰がどのような情報に困っているのかを徹底的に洗い出します。 その上で、新しい案件管理ツールを導入することで、これらの課題をどのように解決し、どのような理想の業務フローを実現したいのかを具体的に設計します。最初から完璧を目指すのではなく、段階的な移行計画を立てることも重要です。 |
| 4. データ移行計画の策定と移行データの品質担保 | 現在Excelや旧システムなどに蓄積されている顧客情報、案件情報、商談履歴といった既存データを、新しい案件管理ツールにどのように移行するのか、具体的な手順、担当者、スケジュールを詳細に計画します。 移行前には、データの重複削除や誤記修正、フォーマット統一といった「データクレンジング」を行ない、移行するデータの品質を高めることが、新ツールでのスムーズなスタートを切るために重要です。 |
| 5. 社内への丁寧な事前説明と「自分ごと化」の促進 | 新しいツールが導入されることに対して、現場の社員が不安や抵抗を感じるのは自然なことです。案件管理ツール導入の目的、それによって得られる現場のメリット、導入スケジュールなどを、事前に複数回に分けて丁寧に説明し、理解と協力を得られるように努めましょう。 「やらされる」のではなく、「自分たちの仕事が楽になる」「成果が上がる」という当事者意識(自分ごと化)を育むコミュニケーションが鍵となります。 |
案件管理ツール導入を検討する適切なタイミングとスムーズな移行の考え方
案件管理ツール選定が完了し、導入へと気持ちが高まる時期ですが、この導入準備フェーズこそ、プロジェクトの成否を左右する最も重要な期間です。
焦らず、以下のポイントを確実に押さえましょう。
| 1. ツールの初期設定と、自社業務に合わせたカスタマイズ | ベンダーの推奨設定を基本としつつ、フェーズ1で設計した理想の業務フローに合わせて、入力項目、選択肢、閲覧・編集権限、通知設定などをカスタマイズします。 最初から複雑な設定にしすぎず、まずは必要最低限の機能でスタートし、運用しながら現場のフィードバックを元に調整していくという考え方も有効です。 |
| 2. データ移行の慎重な実施と移行後の徹底検証 | 策定した計画にもとづき、細心の注意を払いながらデータ移行作業を実施します。移行作業中・移行後には、データが正確に、かつ漏れなく移行されているか、文字化けや項目のズレなどが起きていないかを必ず複数人で検証しましょう。 |
| 3. 一部部門でのテスト運用(パイロット運用)の実施とフィードバック収集 | 全社展開の前に、特定の部門やチームを選定してテスト運用(パイロット運用)を実施し、操作性や設定内容、業務フローに大きな問題がないか、現場目線で評価します。 使いやすい点、分かりにくい点、改善要望など、テストユーザーから具体的なフィードバックを積極的に収集し、本格展開前に必要な調整や改善を行なうことが、その後のスムーズな全社展開に繋がります。 |
| 4. 自社運用に即した利用マニュアルの整備と、実践的な研修の実施 | ベンダー提供のマニュアルだけでなく、自社の具体的な運用ルールや業務フローに合わせた、分かりやすい利用マニュアルを作成・共有します。 システム管理者向けと一般利用者向けに、それぞれの役割に応じた研修プログラムを実施し、案件管理ツールの基本的な操作方法や活用イメージを習得してもらいます。座学だけでなく、実際の業務シナリオにもとづいたハンズオン形式の研修を取り入れると、より実践的で効果が高まります。 |
フェーズ3:ツール定着化・活用促進フェーズ
| 1. 本格的な全社展開と利用ルールの再徹底 | テスト運用での課題をクリアした後、いよいよ全社での利用開始です。改めてツール導入の目的とメリット、そしてたとえば、案件情報は必ず当日中に入力する、顧客とのやり取りはコメント機能に記録するなどの守るべき運用ルールを全社員に周知徹底します。 経営層や各部門のマネージャーが率先して案件管理ツールを活用し、その重要性を現場に示し続けることが、利用文化を醸成するうえで効果的です。 |
| 2. 利用状況の継続的なモニタリングと効果の定期的な見える化 | ログイン頻度、データ入力率、特定機能の活用度など、各部門や個人のツール利用状況を定期的にモニタリングし、利用が滞っている部門や個人がいれば、その原因を特定し、個別のフォローアップや追加研修などを行ないます。 フェーズ1で設定したKPIにもとづき、導入効果を定期的に測定・分析し、その結果を社内で共有することで、案件管理ツールの価値を「見える化」し、さらなる活用意欲を引き出します。 |
| 3. 疑問や不安を解消するヘルプデスク体制の構築とナレッジ共有の促進 | 案件管理ツール利用に関する疑問やトラブルが発生した際に、気軽に相談できる社内ヘルプデスク担当者を設けたり、ベンダーのサポート窓口を明確に案内したりする体制を整えましょう。 よくある質問とその回答をまとめた社内Q&AサイトやFAQページを作成・更新することで、自己解決を促し、問い合わせ対応の負荷を軽減できます。また、便利な使い方や成功事例などのナレッジを共有する場を設けるのも効果的です。 |
| 4. 成功事例の積極的な共有と継続的な改善サイクルの確立 | 案件管理ツールを効果的に活用して、実際に業務効率が上がったり、大きな成果を上げたりした部署や個人の事例を、社内報や会議の場などで積極的に共有し、他のメンバーのモチベーション向上や「自分たちもやってみよう」という活用促進に繋げましょう。 定期的に利用者からの意見や改善要望を収集し、ツールの設定変更、運用ルールの見直し、追加機能の検討など、継続的な改善サイクル(PDCA)を回すことで、ツールを自社の成長に合わせて進化させ、その価値を最大限に高めていくことができます。 |
案件管理ツールの導入は、ゴールではなく、あくまで業務改革のスタートラインです。
組織全体で目的意識を共有し、変化を恐れずに、粘り強く活用と改善を続けることこそが、案件管理ツール導入を真の成功へと導く唯一の道と言えるでしょう。
正確な案件管理には目的に沿ったツールの選択が重要

案件管理は商談の進捗や顧客情報を管理する業務で、適切なタイミングで、効果的なアプローチを実施するために欠かせません。
案件管理の実施で受注確度を見極めたり、営業組織全体で情報を共有したりでき、成約率アップや体制の改善などに効果的です。
一方で、運用体制や要件定義、セキュリティ対策などに不備があるとメリットを期待できないため、案件管理の実施方法・体制をしっかり構築しましょう。
案件管理に活用できるツールはさまざまありますが、どれを選べばいいかわからない人もいるでしょう。
もし悩んでいましたら、月額3,000円で利用できる「Starter Suite」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。案件の進捗状況や顧客情報を管理できるだけではなく、顧客からの問い合わせも漏れなく把握できます。30日間の無料トライアルを実施しているため、まず使ってみたい方は気軽にお申込みください。
関連記事・リソース

無料eBook
SFAを決める前に知っておくべき10の基礎知識
いまから始める営業支援システム

動画
2分でわかるデモ動画
SFAツールを使った案件・商談情報の管理方法

無料ガイド
敏腕営業マネージャー語る
セールスフォース・ジャパンには存在しない営業7つのムダ
関連製品
Essentials
中小企業向けCRM
実現するSFA・カスタマーサービス
Sales
営業支援
スマート、スピーディに営業
まずはご相談ください
弊社のエキスパートがいつでもお待ちしております。